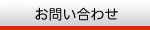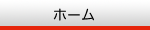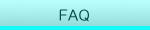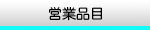V.cとは何か
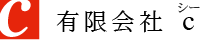


V.cについて詳しく説明する前に、エンタープライズ・システムのことを述べる必要があります。なぜなら、V.cは、エンタープライズ・システムを構成する一部分でもあるからです。
そこで、エンタプライズ・システムとは何か、ということですが、異なるビジネス機能、各ビジネスユニット、それらの隔たりを超えて、情報が「流れる」。 インターネットが組織と組織のコミュニケーションを担うように、このシステムが企業内の情報流通を担う。 善くも悪くも、ビジネス処理全般、顧客取引、購買取引、購買伝票、売上伝票、製造などが、このシステムを通過しないことはない。 結局、企業活動のあらゆるコンピュータ・ベースの情報を、このシステムが提供するということなのです。
そのようなインフォメーション・システムを、エンタープライズ・システム(以後ESと記述する)と呼びます。
ESは、サプライチェーンの最適化、営業のオートメーション化(Sales Force Auto-mation:SFA)、さらに顧客サービスを行う。 これらの新機能の実現は、ESベンダーが提供する統合業務ソフトウエア・パッケージ(Enterprise Resource Planninng:ERP)の導入によって行われることがほとんどです。従ってESは、ERPと同義語のようになっています。
それが最近になって、また、新たなテクノロジーが、フロントオフィスとバックオフィスの壁を大きく取り払いました。 インターネット、そして、インターネットの技術を利用したイントラネットと呼ばれる企業内ネットワークが、情報アクセスを提供する理想的なツールとなった のです。 ブラウザ一つあれば、従業員、サプライヤー、顧客の誰もが、企業の発する情報にアクセスできるのです。では、情報は何処から来るのでしょうか。 インターネット技術自体は、ビジネス取引を処理したり、重要なデータを蓄積したりすることはないのです。 インターネットは、情報アクセス技術なのです。ESこそが、情報処理に最適のシステムであり、インターネットによる内外の情報ニーズに応えるべく、肝心な 情報を産出する工房なのです。 精査されていない低品質の情報を従業員や顧客に流すのは愚かなことです。情報の品質維持と情報アクセスの拡大。 この二点に対して同時に力を注がなければなりません。企業情報のメイン・プラットフォームとしてのES。企業情報へのアクセス方法としてのインターネッ ト。 この二つの融合に成功する者こそが、新世紀をリードする企業なのです。
つまり、ESは、ビジネスがコンピュータに求めるものすべてを、備えているのです。 ESは、誰にでも、情報システム部門の人間だけにではなく、わかりやすい形で、情報を提供する。 ESは、最新のクライアント/サーバ技術を採用し、インターネットとも相乗作用を生む。素晴らしいものです。 では、そんなに、よいことづくめのシステムであるならば、なぜすべての企業、組織は、いますぐにでもESを導入しないのでしょうか。
実際のところ、大企業、中堅企業の多くが、ESを導入しています。しかし、巨額のお金さえ払えば、よいESが手に入るかと言えば、そうではありません。 ESの最も重要で、かつ困難をきたす点は、ビジネスにもたらされる変化です。システム化とは、テクノロジーを一新すると同時にビジネスも一新されるという 点なのです。 たしかに、ES導入の成功には、クライアント/サーバなどの大掛かりな新技術導入を要します。 だが、それ以上に重要で、かつ困難なことは、ビジネスそのものの大幅な変革なのです。
ESを導入した企業のビジネスプロセスは、劇的に変わらなければ、ならないでしょう。 組織、カルチャー、社風、ビジネス戦略に至るまで、すべてをつくり変えることになります。 1990年代初頭に始まった、根本的な企業構造改革へのアプローチとしてのリエンジニアリングは、ES時代の前触れにすぎなかったのです。 事実、ビジネスプロセス・リエンジニアリングのブームは、さらに上を目指すESイニシアティブ(ビジネスバリューを生み出すシステム化)へと移っていま す。 ESプロジェクトは領域が広範囲に及び技術的に複雑なため、最大のリエンジニアリング・プロジェクトよりも難しく、時間も労力も費用も多く費やすことにな ります。
ESが実現すること、それは「確かなつながり」です。 正しく連結された情報により、大袈裟に言えば、世界中の人々が、何をしているかがリアルタイムで、完全に把握できるのです。ビジネス史上、初めてのことで はないでしょうか。 そして、企業はこれまでに経験したことのない事態に、直面することになります。現状を脅かされる、という怖さです。なぜなら、企業は人により成り立ってい るからです。 ES導入でコンピュータやソフトウエアががらりと変わるように、人も根底から変わらなければならないからです。 まさに、その変革の徹底こそが、ESが他のコンピュータ・システムに比べ、チャレンジの魅力にあふれる点であり、尽力に対する報奨を実感できる点なので す。
もちろん、何かを求めれば、リスクは発生するものです。 ESがもたらす効果である品質向上、コスト削減、顧客の満足と定着化を実現できるとしても、そこに至る道程は、あまりにもハイリスク・ハイリターンです。 昨今の経済状況では、なおさらリスクを取ることをためらわせます。
しかし、インフォメーション時代の大いなる野望に応えることができるのは、いかに困難が多かろうともESなのです。 企業のインフォメーション・ニーズに応える統合情報システムという概念は、コンピュータ化の当初より理想としてあったものが、ES以前は実現不可能でし た。 いまでは、必要なビジネスと組織の改革を行いさえすれば、ESにより、望みがかなえられるのです。また、ビジネス競争に勝ち残るためにも、ESは欠かせな いものになるでしょう。
そこで、ESを導入したいが、垣根の高さに逡巡されている企業に、V.c導入の提案となりました。
V.cとは何かの前に、長々とESのことを述べたのは、V.cも、ESを構成する一部分であることから、V.c導入にも、ES導入のときと同様の困難があ るということを、認識していただきたかったからです。 では、なぜES同様の困難があるのに、V.c導入かということですが、それは、導入リスクが抑えられるのと、費用対効果が早期に現れるからです。 理由は、V.cとは何かの説明でわかっていただけるでしょう。
いよいよ、本論のV.cとは何かの説明に入ります。
V.cとは何か。企業が、顧客に提供する商品やサービスの情報を整理してつくる目録を、V.cと呼ぶことにしたのです。
ESを構成する領域の一つ、顧客取引。それの非財務情報を、ビット情報化することなのです。
従来、企業が提供する商品・サービスの情報は、一方的に、企業から消費者に、テレビのコマーシャルや、新聞、雑誌の広告。 それにハウスオーガン、パンフレット、フォルダー、リーフレットなどの印刷物で提供されてきました。
しかし、インターネットが普及し、消費者が購買の主導権を持つ時代に、ふさわしい情報伝達とは、これまでのような一方通行の手段ではダメなことは明白です。
これからは、消費者が望む多チャンネルの情報伝達手段で、双方向に対応できなければ、消費者の満足は得られないのです。
このことを、端的に言うならば、IT(インフォメーションテクノロジー)すなわち、IT(インターネットテクノロジー)に適応できなければならないということです。
従って、V.cでの情報は、紙からウエブへ─【電子パンフレット】。
情報の在り方は、文書一つとっても、これまでと違うものになります。
デジタル時代を迎えてのビジネス文書は、その作り方、見せ方、管理の仕方すべてにパソコンが利用されるようになりました。 従来の文書とは大きく変わってきました。 「紙の文書」であったものが、画面上でしか読まないもの、見ないものも文書と考えられるようになったのです (紙の上で読むだけでなく画面上で読むもの[電子メールやwebページ]も含めて文書と呼ぶ)。 時には文書に音声や動画、静止画までも含まれることがあります。 紙の文書は、最初から順を追って読むのが基本であり、それを前提にして、作られています。 ところが、画面で読む文書は、リンクが張られていれば、別の文書に飛んで、必要な情報に素早くたどり着くことができます。 画面で読む文書には、電子化された文書ならではの、この利点を生かせる作り方が、求められるのです。 文書を作る技術として、これまでの分かりやすい文章作成技術に加えて、物事を構造的にとらえる技術も必要になってきました。
要するに、データの作り方が重要になってきたということです。
文書をインターネットで配信したり、一度作ったデータを、いろいろなメディアで、共通に使ったり、データの組み合わせ(編集)を変えて再利用したりするためには、 そのような要求に対応できるように、データの作り方を工夫しなけれならなのです。
まさに、そのデータの作り方こそ、V.cそのものなのです。
企業にとって、顧客取引の領域は、顧客との接点を担っている最前線です。すでに営業部門や広告宣伝部門に多くの人的資源が投入されています。 また、顧客に情報提供する手段(テレビや新聞、雑誌の広告。それに、いろいろな印刷物)にも金額の多寡は別として、費用が費やされています。
その費用(人的資源も含めて)を、根本的な企業構造改革へのアプローチとして、V.cを取り入れることに振り向けるべきではないでしょうか。
V.c導入は、V.cとEビジネス戦略との連携が、変革の機会をもたらす一方で、V.cと構造や文化との適合は難しく、多くの場合、問題が発生する。 ただし、誤解してはいけないのです。V.cが、これまで不可能だった組織構造をサポートし、組織の文化を希望する方向に変化させていくように導入できるの です。
こうしたアプローチは、組織構造の大改革とは言い難いのですが、業務の共通化・標準化により、コスト削減につながるのです。
通常、V.cと導入企業の組織構造とは好相性になく、むしろ導入時の問題となってしまう場合が多い。組織構造が大きくかかわるという認識に欠けていたり、 あるべき組織形態を実現するための施策がなされない場合。 あるいは、V.cプロジェクトを単なるコンピュータ・システム導入ととらえているため、あるべき組織形態が明確に表現されないし、 それを達成するためのマネジメントもおろそかにされがちなのです。これらの場合。V.c導入は、ほとんど失敗に終わります。
従って、V.cに適合する組織形態にするとともに、全従業員が共通の業務プロセスで同一の情報を活用する全社的な文化になることが必須となるのです。
もちろん、過渡期の環境に対処することを忘れてはなりません。インターネット環境が整うまでは、印刷物も重要な情報伝達手段です。 しばらくは主要な役割を担っていくことになります。従ってV.cは、特にカラー画像の印刷品質を担保しているのです。
もともと印刷の分野は、それぞれのプロセス(原稿、企画、編集、写植、製版、刷版、印刷)が、コンピュータの導入を早くから進めていました。 その印刷業務のデジタル化は、各プロセスの「データをつなぐ」ことがうまくできず、逆に印刷業務トータルで見れば、各プロセスの合理化、 効率化がマイナスに作用していることも、多く見られることです。
従って、一つ目は、最初に入力したデジタルデータを「確かなつながり」で最後まで完結させる。このことが、デジタルの利点を最大限活かすことになるので す。 二つ目は、コンカレントエンジニアリング手法による、各プロセスが並行して作業が行えるメリットをフルに活用する。これもデジタル化の効用です。 以上二点を機能させれば、自然にコスト削減に結び付きます。
印刷業界も「印刷業」から「印刷情報産業」への変革を標榜し、デジタル情報は「ワンソース・マルチユース」であると謳っています。
すなわち「ワンソース・マルチユース」を唱えるのは、他部門、他メディアでも、印刷のデジタル情報が使えるということになります。
しかし、印刷のデジタル情報は、印刷独自のデータ形式になっています。他部門、他メディアでは、使い勝手が悪いのです。そのために 「ワンソース・マルチユース」がなかなか進展しないのではないでしょうか。
それならと、逆に印刷の方が、他部門、他メディアの汎用データを利用することで「ワンソース・マルチユース」が実現するのです。 汎用データから、印刷のデジタルデータを、作り出すということです。それで初めて、印刷情報もマルチメディアの仲間入りとなるのです。
V.cは、デジタル情報のマルチメディア環境を実現するものなのです。
1990年代の後半から始まったIT革命は、ほんの数年のうちに、これまでのビジネスの常識、社会の常識を、ことごとく覆してきました。 多くの企業は、これまで、体験したことのなかった未曾有の変化に直面しています。この劇的な変化が、経営に反映されていない、 あるいは、その準備さえ、されていない企業が、多いのが現状ではないでしょうか。曰く、「まだ早い」「ウチには向いていない」「過去に実績がない」…。 また、その一方では「これからはネットビジネスで…」などと簡単に言ってしまう経営者もおられる。
今日の変化の重大性を認識していないという点で、両者は共通していると言えます。
変化を正確に認識し、的確に対応していく企業だけが勝ち残っていく。 これからの経営者に必要とされるのは、新しい変化を受け入れ、これを積極的に利用していく柔軟性です。 次々に押し寄せる新しい波のなかで、自分の企業がどこに位置し、市場やビジネスがどう変化していくのかを知らなければなりません。 大時化の海上で船を操るように、この荒ぶる波を乗り切っていかなければならないのです。変化は、複合的、重層的に起こっています。 多種多様な変化が、思わぬところで融合しながら、さらに別の変化を引き起こす。それが、IT革命の革命たる所以です。
変化が、複合的に起こるということは、単一の技術の革新が、計り知れない規模の影響をもたらすということでもあります。 過去の実績から、先を見通すのではなく、今起こっていることに、即座に対応する以外、勝ち残る道はないと言っても過言ではないのです。
地理的な条件や資本の規模に依存する、静的な企業形態は、より柔軟な、企業間連携を基礎とする動的な環境に、移行していくでしょう。 また、中長期計画をベースとした経営モデルは、頻繁な変化に対応するために、リアルタイムな変更を余儀なくされるのです。
そのような事態に、ピッタリなのが、私たちの提唱するリンクソーシング組織ではないでしょうか。